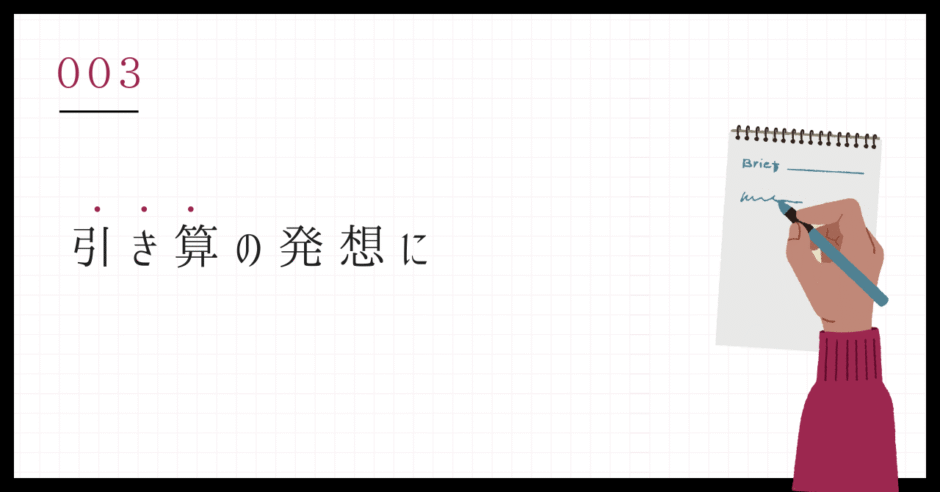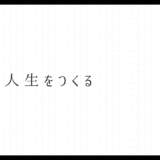目次 閉じる
生きている限り、私たちは必ず課題や問題に直面します。仕事においても「もっと効率的にできればいいのに」と思う瞬間は少なくありません。多くの人は、その解決策を「足す」ことに求めがちです。新しいソフトを導入する、人を増やす、機器を買い足す──こうしたプラスの発想は一見合理的に見えます。
しかし実際には、足した要素を使いこなすために新たな負担が生じ、かえって課題が複雑になることも少なくありません。便利なソフトを導入した結果、操作方法を学ぶために時間を取られたり、別の部署との調整が増えたりする。人員を増やせば、管理や教育のコストが生まれる。つまり「足す」発想は問題を根本的に解決するどころか、別の課題を派生させる危険すらあるのです。
そこで大切になるのが「引く」という発想です。課題に取り組む際には、まず邪魔になっている要素を洗い出し、削ぎ落とすことが有効です。
例えば、マルチタスクに追われて仕事が終わらない場合。多くの人は「もっと効率的に処理できる方法を身につけよう」と考えます。しかし根本的な解決は「優先順位を付け、一つずつ片付ける」ことです。人間は一人しかおらず、同時に処理できることには限界がある。足す努力よりも、余計なものを引き算し、本当に必要なものだけに集中する方が合理的なのです。
これは日常生活にも当てはまります。最近注目されるミニマリストたちは、所有する物を極端に減らすことで、意思決定の負担を軽くし、精神的な自由を手にしています。「あれも欲しい」「これも欲しい」と際限なく買い物をするのは「足す発想」の典型です。逆に「すでにある物で満足する」と決めると、余分な選択肢が消え、生活は驚くほどシンプルになります。
「足すこと」ばかりが進歩だと思われがちですが、実際には「引くこと」が真の解決をもたらします。やっていたことを一つ減らすだけで、やるべきことが明確になり、精神的なゆとりが生まれるのです。
引き算の発想には二つの効果があります。第一に、無駄を省くことで集中力が高まり、生産性が向上すること。第二に、選択肢を減らすことで心が軽くなり、迷いや不安から解放されること。
もちろん、すべてを捨てる必要はありません。大切なのは「本当に必要なものは何か」を見極める視点です。仕事であれば「最優先の課題はどれか」、生活であれば「なくては困る物は何か」。この問いを繰り返すことで、足し算では得られない本質的な解決が見えてきます。
私たちはつい「何かを加えれば状況は良くなる」と考えがちです。しかし、課題解決の本質は「引くこと」にあります。余計なものを削ぎ落とし、必要なものに集中する。その小さな実践が、仕事も生活も大きく変える力を持っているのです。
まずは一つ、これまで当然のように続けていたことをやめてみる。小さな引き算の一歩が、意外なほど大きな余白と豊かさをもたらしてくれるはずです。