目次 閉じる
人は生きている限り、欲望とともに歩んでいます。食欲、睡眠欲、性欲、物欲、承認欲、独占欲──挙げればきりがありません。これらは人を悩ませ、社会にトラブルを引き起こす原因ともなります。ニュースで繰り返し取り上げられる不倫や不正の数々も、突き詰めれば「抑えきれない欲望」の表れでしょう。
しかし一方で、欲望は人を生かす力でもあります。美味しい食事を求める心は生活を彩り、承認を求める気持ちは人との絆を結び、物を欲する心は文化や経済を発展させてきました。欲望は悩みの根源であると同時に、幸福の源泉でもあるのです。
だからこそ私たちは、この二面性に正面から向き合わざるを得ません。欲望をどう扱うかによって、人生は豊かにもなれば、破滅的にもなり得るのです。
仏教においてお釈迦さまは、人間の苦しみの原因を「執着」にあると説きました。
奇なるかな、奇なるかな、一切衆生悉く皆な如来の智慧徳相を具有す。ただ妄想執着あるがゆえに証得せず。
この言葉を現代語にすれば、「人は本来すべて仏と同じ尊い資質を備えている。だが妄想やこだわり、強すぎる欲望に縛られているために、その本質を発揮できない」という意味です。
ここで問題とされているのは、欲望そのものではありません。執着し、しがみつく心です。なかでも他人のものを奪い、際限なく求め続ける「貪欲(とんよく)」は、人を誤った道に導きます。
フランスの哲学者ヴォルテールは「真の欲求なくして真の満足はない」と語りました。これは欲望を全面的に否定するのではなく、人間にとって欲望は欠かせぬものであることを示しています。問題は、その欲望が制御を失ったときに人を縛り、苦しめる点にあります。
心理学においても、マズローの欲求五段階説に見られるように、欲望は人間の成長や自己実現を促す段階的な力と考えられています。すなわち欲望は人間を前に進ませる推進力であると同時に、執着に変われば人を退行させる危険を孕むものなのです。
では私たちは、この尽きることのない欲望とどのように付き合えばよいのでしょうか。
第一に大切なのは、自らに問いかける習慣です。「いま私が求めているものは本当に必要だろうか?」「この欲望は自分を豊かにするのか、それともただの執着ではないのか?」──この問いが、欲望に飲み込まれるか、それを力に変えられるかの分かれ道となります。
第二に、欲望を方向づける工夫が有効です。承認欲を「他者と比べること」ではなく「誰かの役に立つこと」へと転換すれば、欲望は自分も周囲も幸せにする力になります。物欲も「浪費」ではなく「学びや経験への投資」に切り替えることで、自分を成長させる資源となります。
第三に、時には「手放す」練習も必要です。欲しいものをあえて買わない、衝動を一晩寝かせる。その小さな自制心が「欲望を支配する力」を育みます。欲望を完全に消すことはできませんが、距離を置きコントロールすることは可能です。
欲望は生きる力であり、執着は苦しみの種です。貪欲を手放し、欲望を力へと転じる。その一歩を踏み出したとき、人はよりシンプルで豊かな生を歩み始めることができるでしょう。
人間は欲望から逃れることはできません。しかし、欲望に囚われず、それを上手に使いこなすことはできます。貪欲を捨て、自らを豊かにする欲望とだけ共に歩む。その心が、後悔のない人生へと導くはずです。
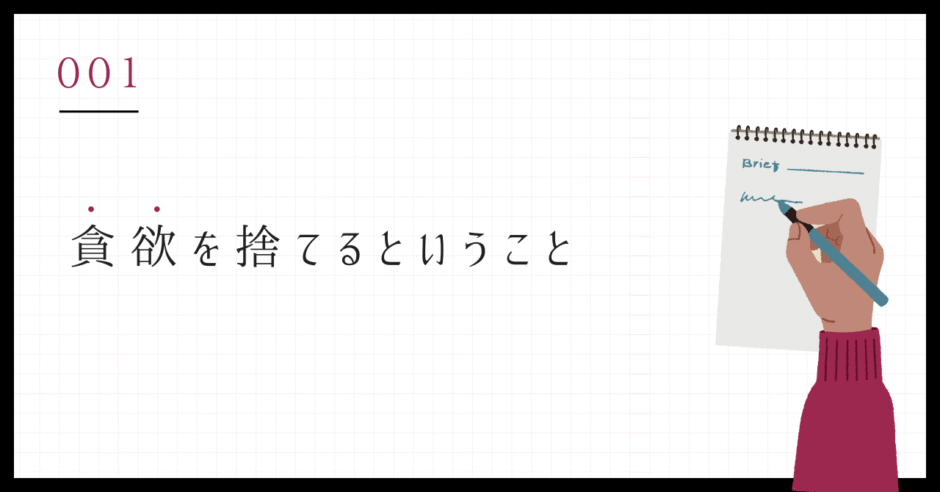

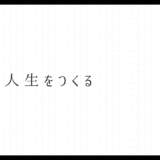
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.