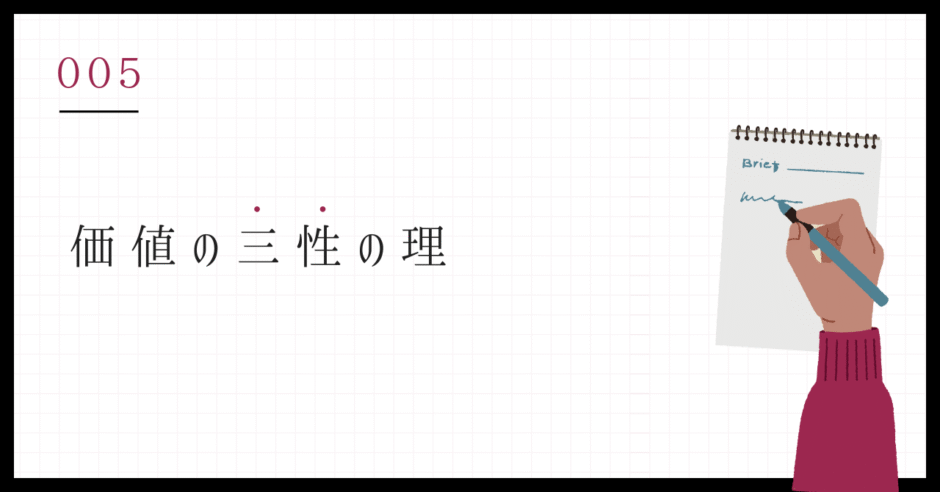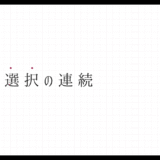東京工業大学名誉教授・森政弘氏は、日本における制御工学の第一人者であり、創作ロボット競技「ロボットコンテスト」の生みの親としても知られています。さらに、人間とロボットの関係を論じる上で世界的に引用される「不気味の谷」理論の提唱者でもあります。ロボット研究の成果を通じて、森氏は常に「人間とは何か」という根本的な問いを追い求めてきました。
その探究の背景にあったのが仏教です。森氏は、学生にものづくりを体験させる授業「乾電池アイデアコンテスト」を実施しましたが、その目的は単なる技術教育にとどまりませんでした。仏教が説く「三昧」の境地──すなわち、作る自分と作られるものとが一体となる状態を学生に体験させること。それが、森氏が教育の根幹に据えた理念でした。
森氏の思想の中核には「一つ」という言葉があります。世界には善と悪、正と負といった対立概念が無数に存在しますが、仏教的な視点に立てば、それらは本来対立するものではなく、ひとつの現実を構成する両面にすぎません。森氏はこの考えを「二元性一原論」と呼びました。
例えばカッターは「切る」という役割を果たしますが、それを機能させるためには「切れない」柄の部分が欠かせません。ハンダごては先端が熱くなければ使えませんが、持ち手まで熱ければ到底使い物にならないでしょう。つまり、相反する性質が同居することで初めて全体としての機能が成立するのです。
この発想は単なる道具の仕組みにとどまらず、世界そのものを読み解く原理へと広がります。善と悪も、快と不快も、相互に切り離せない「一つのもの」として存在している──森氏はそこに仏教的真理を見出したのです。
森氏はさらに「価値の三性」という仏教思想を紹介しています。物事には「善」「悪」だけでなく「無記(むき)」という第三の性質がある、という考え方です。
たとえば、外科医が命を救うために用いる「メス」と、犯罪に使われる「ドス」。両者は善と悪の対極のように見えますが、いずれも素材は同じ鉄であり、もともと善悪の区別はありません。それ自体は「無記」であり、扱う人間の心によって善にも悪にも転じるのです。
森氏は、説教をしながら泥棒を働いた「説教強盗」の逸話を引き合いに出しました。盗みは悪ですが、防犯の知識を最もよく知っていたのは彼であり、後にその知識を人々のために役立てたというのです。ここにも「悪」を「善」に転じる可能性が示されています。
私たちが「これは良い」「あれは悪い」と単純に断じてしまうとき、すでに思考は二元論に縛られています。しかし実際には、すべての事柄は「無記」であり、私たちの心の制御いかんで善にも悪にもなり得るのです。核エネルギーが人類を滅ぼす兵器ともなり、また太陽の恵みとして命を育む力にもなるのは、その典型的な例でしょう。
森政弘氏の思想は、ロボット工学や制御理論といった専門領域を超えて、人間の生き方そのものを問いかけています。二項対立に見えるものを「一つ」として捉え直し、あらゆる事物を「無記」として受けとめる。そして、自らの心の制御によって善なる方向へと転じていく──それが、森氏の語る「仏教的工学」の核心にほかなりません。